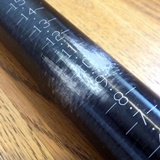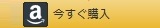DAHON Mu SLX - Specification and Parts -
2019.4.5更新
ダホン(DAHON)の折りたたみ自転車、Mu SLX(2018)の紹介です。
DAHONは、TernやBronptonと並ぶ折りたたみ自転車の巨頭の一角です。 ここで紹介するMu SLXは基本の走行性能の良さ、可搬性、カスタムパーツが豊富なこと、有名メーカーなのでカスタム先駆者も多いことから、 カスタムベースとしても人気のモデルです。 私としては素の状態で気に入ったから買ったようなもので、原型が分からないほどカスタマイズしまくる性分ではありません。 そこまでの情熱と先立物がないという…ですが、機会があれば取り上げたいと思います。
ここで紹介するのはMu SLXの2018年モデルですが、DAHONのMuシリーズ自体は2006年からMu P8、Mu SL、Mu EX、Mu Eliteなど中級〜最上級モデルとして売られ続けています。 2019年モデルのMu SLXも後輪のハブが変わっただけで大きな変更点はないようです。
実は、DAHON.jp のHPから2018年の仕様を見ようと思っても、すでに見ることができません。 URLの西暦を2018に変えれば製品ページには行けますが、仕様を表示させるタブが反応しなくなっています。HTMLタグを読めば分かりますけど…。

《 2018 DAHON Mu SLX テクニカルデータ 》
基本はDAHON.jp から引用ですが意訳や追加情報も掲載しています。



何を以って「μ」のペットネームを付けたのか定かではありませんが、⇒ Wikiへから察するに、 12番目のギリシア文字ということからDAHONの12番目のフレームデザインだったか、国際単位系10の-6乗(ミクロン)から超小型を連想する言葉として用いたか、地面とタイヤの摩擦係数のあたりだと思います。 Horize(水平)みたいにフレームデザインまんまな名前とか、Speed(速さ)やRoute(道)、Curve(曲線)、Boardwalk(坂道)、Vector(方向)みたいにあぁ自転車メーカーだなぁな名前なら分かりやすいのですが。
どうやらペットネームのあとのアルファベットは、
SL(SuperLight):軽量性を重視したヤツ。
…という意味合いのようです。2009年DAHON.jpのMu SLのページに『超軽量(スーパーライト)のMu 軽さこそ最大のポテンシャル!』と書かれていることから、ほぼ間違いないでしょう。
X(eXceed):〜を超えるヤツ・フラグシップモデル。
「X」のほうは、まぁ…extend(拡張版)、excellent(優秀)、experiment(実験機)、excess(過剰性能)など、どれもありそうです。 最初に「Mu SLX」が出た2013年DAHON.jpのMu SLXのページに『昨年までの軽量モデルMu SLを超える超軽量モデルの誕生』という文言があり、 【「SLのさらに上を行く物」を表現するためにXを付加した】とDAHON.jpから回答があったため、exceed(超越)かと予想してみます。
なお「SLX」のアルファベットを冠しているのはMu SLXだけです。SLのほうはMuはもとより、Helios SLやPresto SLに採用例があり、XはVectorやDashにも使われていますが、「SLX」はMuだけのものです。
ええと、DAHONでは、カラー名称にただのブラックとかシルバーとか付けず、「何たらブラック」と気取るのが通例となっています。 ブラック系統に限ってみても、マットブラック(艶消し)なんてかなり分かりやすいほうで、シャドウブラック(陰影)、ニューブラック(新しい)と来て、 極めつけがオブシディアンブラック(黒曜石)で、マットブラックと同じく採用例が多いです。 他にもミクストブラック(雑多)、リキッドブラック(液状)、シルキーブラック(絹)、ナイトブラック(夜)と、もはや何でもありです。DAHONが意地でもそれっぽい名前を付けたかった黒歴史が今ここに。



一番採用例が多いオブシディアンブラックにしても、「あぁこういうカラーデザインをオブシディアンブラックと呼ぶことにしたのね」と分かる統一感があれば突っ込まないで済むのですが、ひょっとして触れないのがお約束なのでしょうか。 ちなみにドレスブラックは「正装の黒」ってことになりますが…本気?
…が、『2018年のMu SLXのモデル番号はPKA015』とDAHON.jpより回答がありました。 また、Amazon.co.jpや家電量販系では「18MUSLBK00」なる型番らしきものが載っていますが、これはDAHON.jp固有の在庫管理番号のようで、本来は社外で使われるものではないそうです。
公式に8.6kgですが、こういうのは車体前後やホイールに付く反射板はもちろん、チェーンリテイナー(チェーン落ち防止パーツ)など走行に支障がないものは除いての重量になるのが通例。 気を付けたいのがペダルで、付属する三ヶ島のプロムナードEzyは公式で351gもあります。ペダルが付属しないロードバイクでペダル抜きの重量を記載するのは仕方ないと思いますが、 ペダルが付属するのに8.6kgを謳うのは眉唾と言われても文句が言えないでしょう。
YAMAZENのデジタル体組成計HCF-36で体重を引いた換算では8.75kg(ペダル込み)でした。想像してたよりも随分と軽いですね。
この軽さの理由としては、「何も足さない・何も引かない」「必要な重さはゼロから足していく」を地で行くシンプルなパーツ構成があります。 カスタム好きな人に言わせればまだまだ軽量化の余地があるように見えると思いますが、ガッツリ削りやすいホイールセット、タイヤ、シートポストはすでに押さえてあります。 ドライブトレインやハンドルバー、ペダル、ブレーキ関連などは上位グレードがあるものの、決して低級なものが付いているわけでもなく、「折りたたみ自転車でやる意義」を問われるラインまで落とし込まれています。 これを軽量化しようにも厳しい道のりになりそうです。
《 フレーム材質 》
アルミ製であること以外は詳細不明…orz この「Dalloy」はどうせDahon alloyのことでしょう。DAHON.comのHPには独自技術を紹介するページがあって、そこには
…とあります(超意訳)。要はDAHON独自のアルミ合金ということです。とは言え、2011年のMu SLまではフレーム欄に「7005 double butted aluminum」と書かれています。 これがDAHON特許技術のDalloyとやらに変わったわけですが、まぁDouble-Butted構造の7005アルミフレームをそう呼んでるだけだろうことは想像に難くありません。7000系アルミが使われているってだけでもスペック的安心感があります。 廉価モデルのRouteのフレーム仕様は「7005 Alloy」とわざわざ別仕様を掲げているので、Dalloy Sonusがただの7005アルミではないことも確実でしょう。
ただし…DAHONの2017年〜2019年製品が合計で44車種のうち、Dalloy Sonus Aluminum採用は29車種と、 7005 AlloyがRoute専用で3車種なのはともかくとしても、他は4130クロモリがSpeed FalcoとBoardwalkに6車種、Dalloy Aluminum Dual Arc DesignがDash系で6車種だから、スペック的に何のありがたみもない状態です。 あくまで同じ材質と製法なだけであって、同じDouble buttedにもパイプ厚の選択や肉抜き加減と精度に差があるはずですが、そのグレード分けみたいのを表記して上位と下位モデルを差別化してもよいのではないでしょうか。 ちなみにDAHON international最上位モデルVigorシリーズには「Hydroformed Dalloy Aluminum」が採用されています。
《 フレームジオメトリ 》
調査中・・・m(_ _)m というか、折りたたみ自転車は一点ものばかりで、自分の体型とジオメトリを比較してメーカーや車種を選ぶような真似は不可能ですから、 調べることにどれだけの意味があるのか甚だ疑問ですが、まぁ自己満足の一環としていつか挙げたいと思います。
《 なんでSonus? 》
ラテン語で音を意味し、英語のSonicの語源。SONY社の由来として有名な言葉ですが、DAHON.jp公式回答で「把握していない」とのこと。マジかよ… orz
《 ヘッドバッジ 》
《 溶接痕のスムージング 》
下位グレードのパーツをアップグレードしてもどうにもならないのがフレームデザインです。よっぽど意識して設計されたもの以外は、折りたたみ自転車である以上はヒンジという目立つ部分があって、その部分は溶接の跡でモリモリしているのが普通です。 まぁDAHONにはLOCK JAWというヒンジが全然目立たない折り畳み方式もあるのですが、2019年のClinch D10、Dash Altenaともヘッドチューブ周りやシートチューブ周りは処理されていません。 通常のDFSで溶接痕のスムージングが成されているのはMu SLXとVisc Evoだけです。まぁMu SLXも完璧ではありません。写真を載せたいと思います。
ヘッドチューブ、折り畳みヒンジ、メインフレームからシートチューブを介してシートステーへ繋がる目立つ部分はキレイに処理されています。 一方で、フロントフォークの二股に分かれる部分と、BB周りは溶接痕がモリモリしていて、ちょっと残念な気分になります。BB周りは技術的に難しい部分とも聞きますが。 フロントやリアのフォークエンドも溶接痕がありますが、そこは目立たない部分ですしあまりうるさく叫ぶつもりもないです。
Radius "Onepiece"なのは、他にRadius Tと、Radius V Telescope、Radius adjustableと兄弟がいるからです。 ハンドルポストの頂上にクランプがあって直接ハンドルバーを固定するタイプがRadius Onepiece、頂上にT字に別パイプが付いていてSyntace VROステムと合わせるのがRadius T、 基本はRadius Onepieceと同じですがハンドルポストが二重構造になってハンドルの高さを調整できるのがRadius V Telescopeです。近年はRadius VをRadius ajustableと呼んでいるようですね。
Right Side Foldingは、そのまま右折れで折り畳まれるタイプであることを示しています。ちなみにOutside Folding(外折れ)と呼ばれていたこともありました。意味は同じです。 これに対するのがLeft Side/Inside(左折れ/内折れ)です。簡単に言えば、ハンドル周りをカスタムしても余裕があるのが外折れ式で、折り畳み時にコンパクトに纏まるのが内折れ式です。上位モデルほど外折れが採用されやすい傾向にあります。
《 ステム − 非搭載 》
《 KALLOY HB-FB12 AL-006 》
⇒ Kalloy HB-FB12 MTBハンドルバー
《 KCNC Lite Wing データ 》
重量内訳は、ヤグラベースが13.2g、チタンボルト+チタンワッシャーが5.6g+4.6g、レール押さえが7.3g x 2です。アルミパイプ本体とチタンボルトを仲立ちしている黒い柱が10.2g。つまりパイプ本体は245.8gですね。
新品時のキレイな外観を保つのは絶望的に難しい。当然ですがシートポストは展開と収納のたびに上げ下げしますし、クランプで締め付けられる場所も一定とは言えません。 下の撮影が購入9ヶ月後、週4で一日あたり展開と収納を4回なので、これまでに600回は上げ下げしていることになります。 我ながら自転車の扱いは割かしズボラなほうで、ピカピカじゃないと嫌というほどではありませんが、うぅん…と唸ってしまう傷付きっぷりです。
どうやらシートポストの汚れは車体やドライブトレイン以上に気を配ったほうがよいようです。 ちょっと晴の日に路上を走るだけでもシートポストを手の平で触れると黒くなることから、相当に汚れやすい部分であること、また汚れたまま展開と収納を繰り返せば摩耗が早まることは想像に難くありません。 週1じゃ足らんですね。小まめに拭くなり洗うなりしましょう。
⇒ ライトウイング [LITE WING] | KCNC公式サイト
《 DDK DDK-9009 データ 》
フォームパッドこそ入っていますがボリュームは薄く全体的に硬めです。合わない人には速攻でダメ出しが来るタイプだと思います。 デザインとしては、割と細身で穴なし溝なしの完全なマットブラックにDAHONのロゴだけという超絶シンプルなのが個人的にツボなのですが、自分には合いませんでした。残念。
⇒ DDK Group Quality Saddles::DDK-9009
《 SHIMANO 105 SL-RS700-R 》
大概の人は、ギアを下げるレバーは親指で押し、ギアを上げるほうは人差し指で引くと思いますが、一応ギアを上げるだけなら両方対応しているということです。
マルチシフトは、ローギアへ戻すレバーを深押しすると最大で4段まで一気に変速できるものです。これは停車時などにかなり重宝します。ただし、一気に4段を変速させるのは無理があり、普通の人は親指の動く範囲的に3段までじゃないかと思います。
マルチリリースは、トップギアへ上げるレバーを深押しすると2段まで一気に変速できるものですが、普通は人差し指で引くレバーに対して、親指で押す方向にしか機能しません。
操作性は可もなく不可もなく。ロードバイクがまだフラットバーだったころに使っていたTIAGRA SL-R440よりは優れたレスポンスですが、このカテゴリーはシマノもあまり本気じゃないのかなぁとも感じますね。
⇒ SHIMANO SL-RS700整備マニュアル(275KB)
⇒ SHIMANO SL-RS700部品展開図(340KB)
《 SHIMANO TIAGRA BL-4700 データ 》
⇒ SHIMANO デュアルピボットキャリパーブレーキ整備マニュアル(1.7MB)
⇒ SHIMANO 基本作業書(4.6MB) ※参考になるのはP.116〜
⇒ SHIMANO BL-4700部品展開図(185KB)
グリップ付属品として、バーエンドキャップも超然シンプルなプラスチック樹脂製で、左右ペアで5g。 グリップもそうですがカスタムが極めて容易で整備不良のリスクもないから、コーディネートしやすい部分です。 ただし小物だからと調子に乗ると洒落にならない重量増になる部分でもあり、ちょっと禁欲的なほうがスマートに感じてしまいます。
グリップとは関係ないですが、コクピット関連の小物としてハンドルポジショナーがあります。 ハンドルポストのクランプを開くとハンドルバーの中央を現場合わせするのが面倒になるため、センターから動かないように印となるパーツです。左右ペアで6g。
《 DAHON Pro406ホイール 》
フロントハブは、[stainless steel cartridge bearings ultralight 58g]を踏襲することは確認できましたが、 58gなんだからアメクラのMicro58をベースに74mm幅の14Hで特注したものだろうと投げかけたら「DAHONオリジナル品です」との回答が。まぁちょっと信じられませんが…(-_-;)。
スポークは、Sapim社製と2015年など随所に書かれていましたし、太さを測定すると両端の太いところで2.0mm、中央で1.5mmだったので、本家HPから探してButted Laserだとアタリを付けました。DAHON.jp公式回答でも「その通り」とのことです。 個人的にはエアロスポークのほうが好みなんですがね…。
《 パナレーサー ミニッツライト 20x1.25 データ 》
5LINKS 169の16x1.25と比べて随分と細いように感じたので測ってみると、幅は30.0mmでした(5LINKS 169は32.5mm)。 いずれにしても700x23Cに乗っていた身としては太く感じます。さらに細い20x1.10や20x1.00も別メーカーならあるようですが、ちょっと入手性が悪いし、クッション性も妥当に感じるので、履き替えるか迷っています。
⇒ 小径車 | 商品紹介 | パナレーサー株式会社
《 FSA Gossamerクランクセット 》
チェーンガードは非搭載。長ズボンでビジネスorカジュアルに乗りたい人は、裾の巻き込みと油汚れに注意です。ちょっとの汚れなんか気にしないぜ!って人も、油断するとマジで裂けます。 ただ、トレッキングパンツを多用するようになってから、なぜか裾が擦り切れることはなくなりました。 それより、チェーンガードがなくてフロントシングルなのは最高っ♪と思うのは、圧倒的なメンテの楽さですね。 ギアの歯を布で挟んで拭くだけ。アウターとインナーの間とか存在しませんし、アウターリングの肉抜きの向こうにインナーリングがあって邪魔とかもないです。マジで楽。
フロントインナーが39Tの700Cロードバイクに乗っていたときも、左STIの不調によりフロントは死んだまま運用して、ほぼ不満なくて、終いにはフロントディレーラーは外していました。 コンパクトドライブが出たときもエントリーロードユーザーにフロントディレーラーの必要性を無理繰り声高に叫んでやいないかとも思ったわけでして、初心者に16段変速より24段変速のほうがウケるのと同じ理由で、なんか余計なものなんじゃないかと。
そりゃお前の脚が塩っぱいだけだ・レースや峠に行くなら必須だろう突っ込みはその通りと受け止めますが。 軽さに寄与しているのも間違いない事実です。フロントシフトレバーとディレーラーが足して約200g、インナーのチェーンリングが約30gにケーブルも足されるわけです。少なくともフロントシングルなら重い変速動作ともおさらばです。
《 SHIMANO 105 RD-5800-SS 》
⇒ SHIMANO ROADリアディレイラー整備マニュアル(1.2MB)
⇒ SHIMANO RD-5800部品展開図(775KB)
《 SHIMANO CN-HG601-11 》
⇒ SHIMANO 11スピードチェーン整備マニュアル(1.2MB)
〈Mu SLXのペダル1回転で進む距離〉
※ペダル1回転で進む距離(m) = タイヤ周長(mm) ÷ リアスプロケットのギア数 × フロントチェーンリングのギア数 × 1,000
※タイヤ周長:20x1.25(ETRTO32-406)=1,450mm。 参考:700x23C=2,096mm
…とはいえ、自分が乗っていたのは4500系TIAGRAコンポのロードバイク。9速、しかもローギアは整備不良で死んでいましたし、フロントはディレーラーを外してインナーしか使わない運用だったので、もう隔世の感があります。 リアの段数が増えると変速する機会も増える、それも9→10速より10→11速のほうが感じやすいとか前に聞いた気がしますが、9→11速ですからね。笑っちゃうくらい変速の機会は増えましたよ。 ギアの守備範囲が狭いというか、ちょっとペダルが重いかな?軽いかな?と感じてシフトチェンジするまでのタイミングが早いし、かなり漕ぐ力を一定に保てるようになりました。
⇒ SHIMANO カセットスプロケット 11スピード整備マニュアル(172KB)
⇒ SHIMANO CS-5800部品展開図(442KB)
というか、DAHONのロゴが入っていますし、見た目はDahon Proの鍛造アルミ製Vブレーキ[Dahon Pro forged ultra light aluminum V brakes]と同じ物じゃないかと思うんですよね…。
《 三ヶ島製作所 プロムナードEzy データ 》
Ezy Superiorを採用しなかったのは英断としたいですね。アダプターにハメるときにパチンと自動でキャップが戻らない不具合レビューがあるのと、 Ezy SuperiorのほうがノーマルEzyより14g重いし、経験上はEzyストッパーを使わなくてもペダルは外れないためです。そもそもストッパーが外しにくすぎるんですよ…。
⇒ PROMENADE Ezy|自転車ペダルの三ヶ島製作所
まず、電車改札内ではフルカバーの輪行バッグがほぼ必須なことから、車体に転がせる構造があっても活用できないことが挙げられます。 また、改札を出ての乗換も長くて300m程度であり、フルカバー輪行袋から出してから転がし、再び収納してから改札を通るのは非常に手間です。 持ち上げて歩いたほうが早いし、それ以上の距離になったら普通に走行したくなるはず。 集合住宅なら、剥き出しの折りたたみ姿のままエレベーターに乗ったりと利点があるのでしょうかね。点字ブロックで躓きそうなくらいLanding Gearの車輪が小さいのも気になります。スーツケースじゃないんだからバランス激悪でしょうに…。
《 チェーンリテーナー 》
《 反射板・呼び鈴 》
これも公式スペックには書かれていません。…というか、おそらく日本で発売(走行する?)する自転車には反射板や呼び鈴を付けなければならない決まり事のようで、どんな自転車を買っても付属します。 付けてくれたのは購入店の橋輪さんでしょう。
正直言って格好悪いですし、こんなものにも確実に重さがあるので、速攻で外しました。 当然法的にアレなので自己責任ですし、クルマを運転する側に立てば反射板の有用性はよく理解できるので反射テープを貼ろうと思います。セーフティライトの日中点灯も習慣になればどうってことないですし。 ベルは、キャットアイのOH-2400をロードバイクから移植です。滅多鳴らすこともないのですが…これもポーズですよね…。

NUVO NH-B405

SATE-LITE SL-121-H


CAT EYE RR-1-BZ

CAT EYE RR-550-WUW/W
http://hasirin.com/index.html
・DAHON OFFICIAL SITE - ダホン 公式サイト
https://www.dahon.jp/index.html
・DAHON International - ダホンインターナショナル公式サイト
https://dahon-intl.jp/
・Folding Bikes by DAHON
https://dahon.com/
・SHIMANO Bike
https://bike.shimano.com/ja-JP/home.html
・SHIMANO Bike マニュアル&技術情報
https://si.shimano.com/#/
・gan well:岩井商会 Kalloy
http://www.iwaishokai.co.jp/list.php?mnfct_id=kalloy
・KCNC公式サイト
https://www.riteway-jp.com/pa/kcnc/
・DDK Group
http://www.activeddk.com/
・パナレーサー株式会社
https://panaracer.co.jp/
・Full Speed Ahead(FSA)
https://www.fullspeedahead.com/ja
・Promax Components
http://www.promaxcomponents.com/
・自転車ペダルの三ヶ島製作所
https://www.mkspedal.com/?q=ja
・American Classic
https://amclassic.com/
・Sapim
https://www.sapim.be/
- Previous -
購入経緯
試乗レポートへ
- Top -
Mu SLX
トップへ
- Next -
日常のメンテ
プチカスタムへ
DAHONは、TernやBronptonと並ぶ折りたたみ自転車の巨頭の一角です。 ここで紹介するMu SLXは基本の走行性能の良さ、可搬性、カスタムパーツが豊富なこと、有名メーカーなのでカスタム先駆者も多いことから、 カスタムベースとしても人気のモデルです。 私としては素の状態で気に入ったから買ったようなもので、原型が分からないほどカスタマイズしまくる性分ではありません。 そこまでの情熱と先立物がないという…ですが、機会があれば取り上げたいと思います。
ここで紹介するのはMu SLXの2018年モデルですが、DAHONのMuシリーズ自体は2006年からMu P8、Mu SL、Mu EX、Mu Eliteなど中級〜最上級モデルとして売られ続けています。 2019年モデルのMu SLXも後輪のハブが変わっただけで大きな変更点はないようです。
もくじ
・DAHONの『 Mu SLX 』という自転車
・購入するまでの経緯
・Mu SLXを試乗した感触
・各部仕様の覚書
・チェーン落ちをどうにかしたい
・純正輪行バッグSlip Bag20"レビュー
・周辺機器&カスタム候補
・ブルホーン化…そして失敗…
・やっぱりブルホーンSTIか
・参考・引用
・購入するまでの経緯
・Mu SLXを試乗した感触
・各部仕様の覚書
・チェーン落ちをどうにかしたい
・純正輪行バッグSlip Bag20"レビュー
・周辺機器&カスタム候補
・ブルホーン化…そして失敗…
・やっぱりブルホーンSTIか
・参考・引用
DAHON Mu SLXの仕様表
2018年DAHON Mu SLX(Dress Black)の仕様表です。メーカーHPを見ればいつでも閲覧できると思いがちですが、経験上はWebページのデータは全然永遠ではありません。 むしろ「いつ消えるか分からない」代物と捉えて、覚書を作っておくことを勧めます。…でないと、何等かのトラブルが発生したときに対応部品が何なのか分からず困ることになります。実は、DAHON.jp のHPから2018年の仕様を見ようと思っても、すでに見ることができません。 URLの西暦を2018に変えれば製品ページには行けますが、仕様を表示させるタブが反応しなくなっています。HTMLタグを読めば分かりますけど…。

| 項 目 | 内 容 | 詳細 |
| 価格 | 192,000円(税抜) | |
| 車体名称 | Mu SLX | ▼ |
| カラー名称 | ドレスブラック | ▼ |
| モデル番号 | PKA015 (18MUSLBK00) | ▼ |
| 車体重量 | 8.6kg | ▼ |
| 折り畳み方式 | DFS(フレーム水平折り・ハンドルポスト横折り・シートポスト下げ) | |
| 変速機構 | 11段(フロント1段 × リア11段) | |
| フレーム | DAHON PKシリーズ Dalloy ソナス アルミ Vクランプヒンジ | ▼ |
| フォーク | DAHON スリップストリーム アルミ | ▼ |
| ハンドルポスト | DAHON ラディアス ワンピース 外折れ式 長さ330mm/角度12° | ▼ |
| ステム | なし | |
| ハンドルバー | DAHONオリジナル:AL-006 540mm コラム径25.4mm | ▼ |
| シートポスト | KCNC ライトウィング(DAHON別注) 33.9mm径×長さ570mm | ▼ |
| サドル | DAHONオリジナル | ▼ |
| シフトレバー | SHIMANO 105 RS-700-R Black ラピッドファイヤープラス | ▼ |
| ブレーキレバー | SHIMANO TIAGRA BL-4700 | ▼ |
| グリップ | DAHONオリジナル | ▼ |
| Fホイール | DAHON Pro 406 14H | ▼ |
| Rホイール | DAHON Pro 406 16H | |
| タイヤ | パナレーサー ミニッツライトPT 20x1.25 | ▼ |
| クランクセット | FSA ゴッサマー(DAHON別注) 55T | ▼ |
| Fディレーラー | なし | |
| Rディレーラー | SHIMANO 105 RD-5800-SS Black | ▼ |
| チェーン | SHIMANO CN-HG601-11 | ▼ |
| スプロケット | SHIMANO 105 CS-5800 11-28T | ▼ |
| ブレーキアーチ | Promax DHV-85 Vブレーキ | ▼ |
| ペダル | MKS プロムナードEZY Black | ▼ |
| 備考 | Landing Gear用の台座・キックスタンド用の台座 | ▼ |
| 付属品 | 反射板・呼び鈴・チェーンリテーナー |
車体名称 − Mu SLX
このMu(ミュー)は「μ」から来ているのは確実で、2013年にロゴが「やや筆記体調の大文字エム・小文字ユー」になる前は、「mμ」のμが小文字のyみたいに崩した意匠のロゴでした。 実は現行でもロゴは二種類あって、2019 Mu D9や以前のMu P9といった下位モデルでは「mu」みたいなロゴになっています。 おそらく、高級感を出したい上位モデルとポップな感じを出したい普及モデルの間で、ロゴデザインに迷いがあるのでしょう。


何を以って「μ」のペットネームを付けたのか定かではありませんが、⇒ Wikiへから察するに、 12番目のギリシア文字ということからDAHONの12番目のフレームデザインだったか、国際単位系10の-6乗(ミクロン)から超小型を連想する言葉として用いたか、地面とタイヤの摩擦係数のあたりだと思います。 Horize(水平)みたいにフレームデザインまんまな名前とか、Speed(速さ)やRoute(道)、Curve(曲線)、Boardwalk(坂道)、Vector(方向)みたいにあぁ自転車メーカーだなぁな名前なら分かりやすいのですが。
どうやらペットネームのあとのアルファベットは、
SL(SuperLight):軽量性を重視したヤツ。
…という意味合いのようです。2009年DAHON.jpのMu SLのページに『超軽量(スーパーライト)のMu 軽さこそ最大のポテンシャル!』と書かれていることから、ほぼ間違いないでしょう。
X(eXceed):〜を超えるヤツ・フラグシップモデル。
「X」のほうは、まぁ…extend(拡張版)、excellent(優秀)、experiment(実験機)、excess(過剰性能)など、どれもありそうです。 最初に「Mu SLX」が出た2013年DAHON.jpのMu SLXのページに『昨年までの軽量モデルMu SLを超える超軽量モデルの誕生』という文言があり、 【「SLのさらに上を行く物」を表現するためにXを付加した】とDAHON.jpから回答があったため、exceed(超越)かと予想してみます。
なお「SLX」のアルファベットを冠しているのはMu SLXだけです。SLのほうはMuはもとより、Helios SLやPresto SLに採用例があり、XはVectorやDashにも使われていますが、「SLX」はMuだけのものです。
カラー名称 − ドレスブラック(Dress Black)
あまり真面目に考えないほうが吉 (^ー^;)…なのも分かっていますけども。ええと、DAHONでは、カラー名称にただのブラックとかシルバーとか付けず、「何たらブラック」と気取るのが通例となっています。 ブラック系統に限ってみても、マットブラック(艶消し)なんてかなり分かりやすいほうで、シャドウブラック(陰影)、ニューブラック(新しい)と来て、 極めつけがオブシディアンブラック(黒曜石)で、マットブラックと同じく採用例が多いです。 他にもミクストブラック(雑多)、リキッドブラック(液状)、シルキーブラック(絹)、ナイトブラック(夜)と、もはや何でもありです。DAHONが意地でもそれっぽい名前を付けたかった黒歴史が今ここに。



←DAHONのBlackだけでもこんなにある
一番採用例が多いオブシディアンブラックにしても、「あぁこういうカラーデザインをオブシディアンブラックと呼ぶことにしたのね」と分かる統一感があれば突っ込まないで済むのですが、ひょっとして触れないのがお約束なのでしょうか。 ちなみにドレスブラックは「正装の黒」ってことになりますが…本気?
モデル番号 − PKA 015
モデル(Model.)と表現されています。取説というか保証書には車体識別番号こそ書かれていますが型番はありません。 でもフレームに型番が存在するのは確信があって、2014年まではDAHON.jpのHPにもMu SLXは「PKA005」という英数字が書かれていました。 同時にフレーム仕様にもPKシリーズという文言があり、フレーム形状が違うとこのアルファベットも異なっていたのです。例えば2014年のMu EliteはPDA005、Mu P9はPAA093です。 2013年と2014年のMu SLXはパーツ構成が微妙に異なっていても同じPKA005と書かれていることから、フレーム型番と判断したわけです。 ただし2015年のMu SLXからシートステーが細い別フレームになっているので、現行のMuフレームの型番はやはり不明でした。…が、『2018年のMu SLXのモデル番号はPKA015』とDAHON.jpより回答がありました。 また、Amazon.co.jpや家電量販系では「18MUSLBK00」なる型番らしきものが載っていますが、これはDAHON.jp固有の在庫管理番号のようで、本来は社外で使われるものではないそうです。
車体重量 − 8.6kg w/o pedals
繰り返しになりますが、Mu SLXを語るうえで絶対に外せないのが8.6kgという軽さです。巷には7kgを切る折りたたみ自転車もありますが、大概は14インチや16インチホイールで変速なしのモデル。 つまり走行性能を大きく犠牲にしたものです。それに対してMu SLXは20インチ11段変速の8.6kgであり、 走行性や操縦性も…まぁ50km/hとか平気で出しちゃうガチレーサーや100kmじゃまだまだ短距離なロングライダーにはウケないでしょうが… 700Cクロスバイクやルック車に毛が生えたようなロードバイクでそこそこ満足とか、昔はロードバイクでブイブイいわせてたけど歳でもう乗れないなぁ…な人とかには十分に「これはこれでアリ」と納得できるものがあります。公式に8.6kgですが、こういうのは車体前後やホイールに付く反射板はもちろん、チェーンリテイナー(チェーン落ち防止パーツ)など走行に支障がないものは除いての重量になるのが通例。 気を付けたいのがペダルで、付属する三ヶ島のプロムナードEzyは公式で351gもあります。ペダルが付属しないロードバイクでペダル抜きの重量を記載するのは仕方ないと思いますが、 ペダルが付属するのに8.6kgを謳うのは眉唾と言われても文句が言えないでしょう。
YAMAZENのデジタル体組成計HCF-36で体重を引いた換算では8.75kg(ペダル込み)でした。想像してたよりも随分と軽いですね。
この軽さの理由としては、「何も足さない・何も引かない」「必要な重さはゼロから足していく」を地で行くシンプルなパーツ構成があります。 カスタム好きな人に言わせればまだまだ軽量化の余地があるように見えると思いますが、ガッツリ削りやすいホイールセット、タイヤ、シートポストはすでに押さえてあります。 ドライブトレインやハンドルバー、ペダル、ブレーキ関連などは上位グレードがあるものの、決して低級なものが付いているわけでもなく、「折りたたみ自転車でやる意義」を問われるラインまで落とし込まれています。 これを軽量化しようにも厳しい道のりになりそうです。
フレーム − Dalloy Sonus Aluminum V-Clamp Technology
《 フレーム材質 》
アルミ製であること以外は詳細不明…orz この「Dalloy」はどうせDahon alloyのことでしょう。DAHON.comのHPには独自技術を紹介するページがあって、そこには
|
特許技術のDalloyアルミは、6061アルミと比べて20%以上のフレーム強度を実現。 重量を抑えるためにパイプの末端は肉厚で中心に連れて薄くなるダブルバテッド構造を採用。 |
…とあります(超意訳)。要はDAHON独自のアルミ合金ということです。とは言え、2011年のMu SLまではフレーム欄に「7005 double butted aluminum」と書かれています。 これがDAHON特許技術のDalloyとやらに変わったわけですが、まぁDouble-Butted構造の7005アルミフレームをそう呼んでるだけだろうことは想像に難くありません。7000系アルミが使われているってだけでもスペック的安心感があります。 廉価モデルのRouteのフレーム仕様は「7005 Alloy」とわざわざ別仕様を掲げているので、Dalloy Sonusがただの7005アルミではないことも確実でしょう。
ただし…DAHONの2017年〜2019年製品が合計で44車種のうち、Dalloy Sonus Aluminum採用は29車種と、 7005 AlloyがRoute専用で3車種なのはともかくとしても、他は4130クロモリがSpeed FalcoとBoardwalkに6車種、Dalloy Aluminum Dual Arc DesignがDash系で6車種だから、スペック的に何のありがたみもない状態です。 あくまで同じ材質と製法なだけであって、同じDouble buttedにもパイプ厚の選択や肉抜き加減と精度に差があるはずですが、そのグレード分けみたいのを表記して上位と下位モデルを差別化してもよいのではないでしょうか。 ちなみにDAHON international最上位モデルVigorシリーズには「Hydroformed Dalloy Aluminum」が採用されています。
《 フレームジオメトリ 》
調査中・・・m(_ _)m というか、折りたたみ自転車は一点ものばかりで、自分の体型とジオメトリを比較してメーカーや車種を選ぶような真似は不可能ですから、 調べることにどれだけの意味があるのか甚だ疑問ですが、まぁ自己満足の一環としていつか挙げたいと思います。
《 なんでSonus? 》
ラテン語で音を意味し、英語のSonicの語源。SONY社の由来として有名な言葉ですが、DAHON.jp公式回答で「把握していない」とのこと。マジかよ… orz
《 ヘッドバッジ 》
DAHON Mu SLXのヘッドハッジ。30周年(2013年)のときは、ほぼ全車種で記念エンブレムを配したバッジがヘッドチューブかシートチューブに採用されていましたが、35周年であるはずの2018年のMu SLXは普通のヘッドハッジです。
まぁ個人的にはこういった「限定」には思い入れがありません。そのときは良い気分なこともありますが、時が経つと古さの象徴と化すためです。
ちなみに前カゴなどを付けられるアタッチメント ラゲッジトラス(Valetトラス)はありません。
まぁ個人的にはこういった「限定」には思い入れがありません。そのときは良い気分なこともありますが、時が経つと古さの象徴と化すためです。
ちなみに前カゴなどを付けられるアタッチメント ラゲッジトラス(Valetトラス)はありません。
《 溶接痕のスムージング 》
下位グレードのパーツをアップグレードしてもどうにもならないのがフレームデザインです。よっぽど意識して設計されたもの以外は、折りたたみ自転車である以上はヒンジという目立つ部分があって、その部分は溶接の跡でモリモリしているのが普通です。 まぁDAHONにはLOCK JAWというヒンジが全然目立たない折り畳み方式もあるのですが、2019年のClinch D10、Dash Altenaともヘッドチューブ周りやシートチューブ周りは処理されていません。 通常のDFSで溶接痕のスムージングが成されているのはMu SLXとVisc Evoだけです。まぁMu SLXも完璧ではありません。写真を載せたいと思います。
ヘッドチューブ、折り畳みヒンジ、メインフレームからシートチューブを介してシートステーへ繋がる目立つ部分はキレイに処理されています。 一方で、フロントフォークの二股に分かれる部分と、BB周りは溶接痕がモリモリしていて、ちょっと残念な気分になります。BB周りは技術的に難しい部分とも聞きますが。 フロントやリアのフォークエンドも溶接痕がありますが、そこは目立たない部分ですしあまりうるさく叫ぶつもりもないです。
フロントフォーク − Slip Stream Aluminum
公表されてませんがDalloy製(DAHON.jpより)です。 Vブレーキ台座があるエンド幅74mmのベントフォークという以外は、実質的にブラックボックスです。ハンドルポスト − Radius Onepiece R-Side Folding 330mm/12°
これまた名前の由来からして不明…ですが、Radiusは「円の半径」を示す英語で、"r"で数学や図面の記号として馴染みがある人はあるでしょう。
推測になりますが、ハンドルポストの折り畳み動作の上で、円の中心が折り畳みヒンジで、ハンドルバー(ステム)が円の弧、そしてハンドルポストが半径に当たるためと思われます。
考えてみればそのものズバリですね。逆にヒンジで折れるタイプのハンドルポストを採用しながらRadiusの名を冠していないものはありません。
Radius "Onepiece"なのは、他にRadius Tと、Radius V Telescope、Radius adjustableと兄弟がいるからです。 ハンドルポストの頂上にクランプがあって直接ハンドルバーを固定するタイプがRadius Onepiece、頂上にT字に別パイプが付いていてSyntace VROステムと合わせるのがRadius T、 基本はRadius Onepieceと同じですがハンドルポストが二重構造になってハンドルの高さを調整できるのがRadius V Telescopeです。近年はRadius VをRadius ajustableと呼んでいるようですね。
Right Side Foldingは、そのまま右折れで折り畳まれるタイプであることを示しています。ちなみにOutside Folding(外折れ)と呼ばれていたこともありました。意味は同じです。 これに対するのがLeft Side/Inside(左折れ/内折れ)です。簡単に言えば、ハンドル周りをカスタムしても余裕があるのが外折れ式で、折り畳み時にコンパクトに纏まるのが内折れ式です。上位モデルほど外折れが採用されやすい傾向にあります。
《 ステム − 非搭載 》
Radius Onepieceなのでステムなしに直接ハンドルバーを固定できます。Radius Tに比べて機能が省かれているようにも思えますが、実態はハンドルポスト自体が折りたたみ機構を有した長大なアヘッドステムと言えます。
それが高さ330mm・角度12°の部分です。DAHONの特許も絡む専用品なので交換パーツの入手が厳しく、前傾ポジションの決定には難があります。
自分としてはハンドルが気持ち近く30mmほど低くあればと思うので、300mm・12°があるなら欲しいですね。
ハンドルバー − 公式名称なし
ストレート形状でアルミ製・幅540mm・バックスウィーブ8°のハンドルバーが搭載されています。
グリップを外すと末端に「AL-006」という型番っぽい印字が見えるので、おそらくKALLOYのHB-FB12 AL-006がベースではないかと思われます。ただ実測で189gだったので、公称重量とは随分と違うことに。
まぁ別段どうということもないハンドルバーです。普通にグリップを付ければ隠れてしまう型番を除けば、クランプするセンターを示す印字や角度を示す目盛り線などもありません。かなりシンプルです。
まぁ別段どうということもないハンドルバーです。普通にグリップを付ければ隠れてしまう型番を除けば、クランプするセンターを示す印字や角度を示す目盛り線などもありません。かなりシンプルです。
| タイプ | ストレート |
| 材質 | アルミ |
| 横幅 | 540mm |
| クランプ径 | 25.4mm |
| エンド径 | 22.2mm |
| 角度 | バックスウィーブ8° |
| 公称重量 | 167g(580mm) |
| 実測重量 | 189g |
⇒ Kalloy HB-FB12 MTBハンドルバー
シートポスト − KCNC Lite Wing Dahon Edition 33.9 x 570mm
Mu SLXが軽い理由その1。アップグレード候補がないほどの最上級シートポスト、KCNCライトウィングを最初から搭載しています。
DAHONロゴが入っているだけでDAHON Editionなのかな?と思いますが、KCNCのHPからスペックを見れば全長550mmと2cm短いので、そのあたりかもしれませんね。
ヤグラは細かくサドルの角度を決められる2本締めタイプで、もうこれ以上どう簡略化すればよいのか分からないほどシンプルです。ネジはチタン製で、前後で違う長さを採用する徹底っぷり。
長さの570mmについて、上はヤグラのU字型ベースがハマる底から、下はパイプ末端の石突プラパーツを除いたところまでです。
ヤグラは細かくサドルの角度を決められる2本締めタイプで、もうこれ以上どう簡略化すればよいのか分からないほどシンプルです。ネジはチタン製で、前後で違う長さを採用する徹底っぷり。
長さの570mmについて、上はヤグラのU字型ベースがハマる底から、下はパイプ末端の石突プラパーツを除いたところまでです。
| 項 目 | 内 容 |
| ヤグラ | 2本締め |
| 全長 | 570mm |
| 口径 | 33.9mm |
| 材質 | 7075アルミ合金 チタンボルト |
| 公称重量 | 300g |
| 実測重量 | 294g |
重量内訳は、ヤグラベースが13.2g、チタンボルト+チタンワッシャーが5.6g+4.6g、レール押さえが7.3g x 2です。アルミパイプ本体とチタンボルトを仲立ちしている黒い柱が10.2g。つまりパイプ本体は245.8gですね。
新品時のキレイな外観を保つのは絶望的に難しい。当然ですがシートポストは展開と収納のたびに上げ下げしますし、クランプで締め付けられる場所も一定とは言えません。 下の撮影が購入9ヶ月後、週4で一日あたり展開と収納を4回なので、これまでに600回は上げ下げしていることになります。 我ながら自転車の扱いは割かしズボラなほうで、ピカピカじゃないと嫌というほどではありませんが、うぅん…と唸ってしまう傷付きっぷりです。
どうやらシートポストの汚れは車体やドライブトレイン以上に気を配ったほうがよいようです。 ちょっと晴の日に路上を走るだけでもシートポストを手の平で触れると黒くなることから、相当に汚れやすい部分であること、また汚れたまま展開と収納を繰り返せば摩耗が早まることは想像に難くありません。 週1じゃ足らんですね。小まめに拭くなり洗うなりしましょう。
⇒ ライトウイング [LITE WING] | KCNC公式サイト
サドル − 公式名称なし
おそらく2016 Mu SLXのスペック欄にあるLFレースサドル(LF Race Saddle)とDAHONが呼んでいるものじゃないかと思います。その実態は、DDKのDDK-9009というサドルと同型で、そのDAHON別注カラーでしょう。
根拠としては、サドル裏にDDKのロゴがあり、DDKのHPから特長的なテール形状を持つサドルがDDK-9009しか該当するものがないためです。製品ページを実物と比べてもそっくりです。
| 項 目 | 内 容 |
| サイズ | 283 x 138mm |
| レール材質 | 中空クロモリ |
| 公称重量 | 240g |
| 実測重量 | 246g |
フォームパッドこそ入っていますがボリュームは薄く全体的に硬めです。合わない人には速攻でダメ出しが来るタイプだと思います。 デザインとしては、割と細身で穴なし溝なしの完全なマットブラックにDAHONのロゴだけという超絶シンプルなのが個人的にツボなのですが、自分には合いませんでした。残念。
⇒ DDK Group Quality Saddles::DDK-9009
シフター − SHIMANO 105 SL-RS700-R
SHIMANO唯一の11s用シフトレバー、SL-RS700-R Blackです。5800とかR7000の型番からは外れていますが、
SHIMANOのHPかられっきとした5800系105シリーズの一角であることが分かります。
これ以外の11sだとDURA-ACEのバーコンSL-BSR1とかになってしまいます。
まぁ公式以外の変則的に組み合わせる人も居るでしょうけど…
シマノのラピッドファイアープラスは面白いもので、トップ方向へギアを上げるレバーは押しても引いても作動します。2ウェイリリースという機能です。
シマノのラピッドファイアープラスは面白いもので、トップ方向へギアを上げるレバーは押しても引いても作動します。2ウェイリリースという機能です。
| 項 目 | 内 容 |
| グレード | 5800系105 |
| 対応RD | ロード用11スピード |
| クランプ径 | 22.2mm |
| マルチシフト | 最大4 |
| マルチリリース | 親指プッシュのみ2 |
| 機能 | マルチシフト、2ウェイリリース、 マルチリリース、ケーブルアジャスト |
| 公称重量 | 左右210g |
大概の人は、ギアを下げるレバーは親指で押し、ギアを上げるほうは人差し指で引くと思いますが、一応ギアを上げるだけなら両方対応しているということです。
マルチシフトは、ローギアへ戻すレバーを深押しすると最大で4段まで一気に変速できるものです。これは停車時などにかなり重宝します。ただし、一気に4段を変速させるのは無理があり、普通の人は親指の動く範囲的に3段までじゃないかと思います。
マルチリリースは、トップギアへ上げるレバーを深押しすると2段まで一気に変速できるものですが、普通は人差し指で引くレバーに対して、親指で押す方向にしか機能しません。
操作性は可もなく不可もなく。ロードバイクがまだフラットバーだったころに使っていたTIAGRA SL-R440よりは優れたレスポンスですが、このカテゴリーはシマノもあまり本気じゃないのかなぁとも感じますね。
⇒ SHIMANO SL-RS700整備マニュアル(275KB)
⇒ SHIMANO SL-RS700部品展開図(340KB)
ブレーキレバー − SHIMANO TIAGRA BL-4700
ここは105じゃなくてTIAGRAグレードのBL-4700ブレーキレバー。
…というのも、105グレードのBL-R550がなぜかVブレーキに対応していないため、105で揃えられないのです。上位のULTEGRA BL-R780はVブレーキ対応なのに…こちらはブラックカラーのレバーが黒くないという罠が。
そしてULTEGRA BL-R780もTIAGRA BL-4700も重さは変わらないという…。まぁ操作感とかどれだけ違うのかって話でもあります。
実はこのBL-4700、微妙に黒くなく、昔の6600系ULTEGRA-SLみたいに青みがかっています。
実はこのBL-4700、微妙に黒くなく、昔の6600系ULTEGRA-SLみたいに青みがかっています。
| 項 目 | 内 容 |
| 対応ブレーキ | Vブレーキ・メカニカルディスク ・キャリパー・カンチ |
| カラー | 名称なし(ブラック) |
| 対応ワイヤー | Tタイプ |
| クランプ径 | 22.2mm |
| レバーサイズ | 2.5フィンガー |
| 機能 | ブレーキラインアジャスター レバーリーチアジャスター バンパーストップ |
| 実測重量 | ペア168g w/o ケーブル |
⇒ SHIMANO デュアルピボットキャリパーブレーキ整備マニュアル(1.7MB)
⇒ SHIMANO 基本作業書(4.6MB) ※参考になるのはP.116〜
⇒ SHIMANO BL-4700部品展開図(185KB)
グリップ − 公式名称なし
公式名称なし…ですが、VELO社のProlite Formではないかと専らの噂(笑)。まぁVELO社のHPで確認できないのですが、ややコシがあるだけのスポンジですね。 長い距離を走る人はERGONとかに交換しましょう。若干滑りやすいかと思いますが、短距離なら標準ママでも全然問題ないんじゃないかと。何といっても軽いですし。グリップ付属品として、バーエンドキャップも超然シンプルなプラスチック樹脂製で、左右ペアで5g。 グリップもそうですがカスタムが極めて容易で整備不良のリスクもないから、コーディネートしやすい部分です。 ただし小物だからと調子に乗ると洒落にならない重量増になる部分でもあり、ちょっと禁欲的なほうがスマートに感じてしまいます。
グリップとは関係ないですが、コクピット関連の小物としてハンドルポジショナーがあります。 ハンドルポストのクランプを開くとハンドルバーの中央を現場合わせするのが面倒になるため、センターから動かないように印となるパーツです。左右ペアで6g。
ホイールセット − DAHON Pro 406
20インチ(ETRTO406)サイズの軽量アルミ製ホイールセット。Mu SLXが軽い理由その2です。カタログスペックには「DAHON Pro 406」としか表記がありませんが、実測と推測、DAHON.jpへの問い合わせ結果から概ねのところが判明します。
リムは、アルミ合金でH/Eのクリンチャータイヤ対応、リムブレーキ対応です。リム幅19.2mm・リムの高さ26.1mmとディーブでもない普通の高さですが、断面は台形よりは二次曲線を描くエアロに近いシャープな形状です。
リアハブはAmerican Classic(アメクラ)社製で、2015年Mu SLXスペックに[stainless steel cartridge bearings 205g]とあることから、アメクラのRD205ではないかと。 結果として2015年スペックは現行のDAHON Proホイールでも踏襲すると確認でき、RD205をベースにスポーク穴数を16Hに減らした特注品ということでした。ベアリングはセラミック製とかではないようですね。
リムは、アルミ合金でH/Eのクリンチャータイヤ対応、リムブレーキ対応です。リム幅19.2mm・リムの高さ26.1mmとディーブでもない普通の高さですが、断面は台形よりは二次曲線を描くエアロに近いシャープな形状です。
リアハブはAmerican Classic(アメクラ)社製で、2015年Mu SLXスペックに[stainless steel cartridge bearings 205g]とあることから、アメクラのRD205ではないかと。 結果として2015年スペックは現行のDAHON Proホイールでも踏襲すると確認でき、RD205をベースにスポーク穴数を16Hに減らした特注品ということでした。ベアリングはセラミック製とかではないようですね。
| 項 目 | 内 容 |
| 表記サイズ | 20インチ(ETRTO:406) |
| リムタイプ | クリンチャーH/E |
| リム幅 | 外19.2mm |
| リム高さ | 26.1mm |
| フロントハブ | DAHONオリジナル |
| リアハブ | American Classic社 RD205 |
| 対応 スプロケット | SHIMANO/SRAM 9-11s, Campagnolo 10-11s |
| OLD | F:74mm ・ R:130mm |
| スポーク | Sapim社 Butted Laser |
| スポーク数 | F:14H ・ R:16H |
| 公称重量 | 前後セット1180g |
フロントハブは、[stainless steel cartridge bearings ultralight 58g]を踏襲することは確認できましたが、 58gなんだからアメクラのMicro58をベースに74mm幅の14Hで特注したものだろうと投げかけたら「DAHONオリジナル品です」との回答が。まぁちょっと信じられませんが…(-_-;)。
スポークは、Sapim社製と2015年など随所に書かれていましたし、太さを測定すると両端の太いところで2.0mm、中央で1.5mmだったので、本家HPから探してButted Laserだとアタリを付けました。DAHON.jp公式回答でも「その通り」とのことです。 個人的にはエアロスポークのほうが好みなんですがね…。
タイヤ − Panaracer Minits Lite PT 20x1.25 F/V
小径車で最初から付いているタイヤと言えばPanaracer、Schwalbe、KENDAの3社。パナレーサーのミニッツライトはロードタイヤの技術を取り入れた軽量仕様で、20x1.25で公称170g。
同社の耐パンク重視のミニッツタフは240g、コスパ重視のミニッツSは380gです。
安いタイヤと比べると前後で400g以上は違ってくるというMu SLXが軽い理由その3ですが、理論上ロードの700Cより1.3倍の早さで擦り減るから、次回の後輪はミニッツタフでも…とか考えてしまいます。
ミニッツライトは完全なスリックタイヤで、一切の溝やブロックがありません。
ミニッツライトは完全なスリックタイヤで、一切の溝やブロックがありません。
| 項 目 | 内 容 |
| タイプ | クリンチャー H/E |
| ビート | フォールディング |
| 品番 | F20125BAX-MNL4 |
| 表記サイズ | 20 x 1.25(ETRTO:32-406) |
| 幅 | 32mm |
| ビート径 | 406mm |
| カラー | トレッド:ブラック/サイド:ブラック |
| 重量 | 170g |
| 推奨内圧 | 4.5〜7.0 bar/65〜100 PSI |
5LINKS 169の16x1.25と比べて随分と細いように感じたので測ってみると、幅は30.0mmでした(5LINKS 169は32.5mm)。 いずれにしても700x23Cに乗っていた身としては太く感じます。さらに細い20x1.10や20x1.00も別メーカーならあるようですが、ちょっと入手性が悪いし、クッション性も妥当に感じるので、履き替えるか迷っています。
⇒ 小径車 | 商品紹介 | パナレーサー株式会社
クランクセット − FSA Gossamer Dahon Edition 55T
これも実質的にブラックボックス。FSA Gossamer 55Tが搭載されています。FSA自体はクランクをはじめとした自転車パーツメーカーの大御所ですが、手広くやっているだけあってパーツグレードもピンキリで、このクランクがどの程度のものなのかははっきりしません。
ちなみにクランクアームにはCK-602という刻印があり、クランク長は170mmのようです。
55Tのチェーンリングには裏面にWA334-55Tの刻印があり、PCD(BCD)が130mmであることを示す印字があります。
55Tのチェーンリングには裏面にWA334-55Tの刻印があり、PCD(BCD)が130mmであることを示す印字があります。
| 項 目 | 内 容 |
| アーム数 | 5スパイダー |
| PCD | 130mm |
| クランク長 | 170mm |
| チェーンリング | 55T |
| 対応BB | ISIS Drive |
チェーンガードは非搭載。長ズボンでビジネスorカジュアルに乗りたい人は、裾の巻き込みと油汚れに注意です。ちょっとの汚れなんか気にしないぜ!って人も、油断するとマジで裂けます。 ただ、トレッキングパンツを多用するようになってから、なぜか裾が擦り切れることはなくなりました。 それより、チェーンガードがなくてフロントシングルなのは最高っ♪と思うのは、圧倒的なメンテの楽さですね。 ギアの歯を布で挟んで拭くだけ。アウターとインナーの間とか存在しませんし、アウターリングの肉抜きの向こうにインナーリングがあって邪魔とかもないです。マジで楽。
フロントディレーラー − 非搭載
台座のみでフロントディレーラーは付いていません。フロントシングルです。あるべき機能がないように思う人も居るかもしれませんが、実際問題として「フロントを変速するか」という話になります。フロントインナーが39Tの700Cロードバイクに乗っていたときも、左STIの不調によりフロントは死んだまま運用して、ほぼ不満なくて、終いにはフロントディレーラーは外していました。 コンパクトドライブが出たときもエントリーロードユーザーにフロントディレーラーの必要性を無理繰り声高に叫んでやいないかとも思ったわけでして、初心者に16段変速より24段変速のほうがウケるのと同じ理由で、なんか余計なものなんじゃないかと。
そりゃお前の脚が塩っぱいだけだ・レースや峠に行くなら必須だろう突っ込みはその通りと受け止めますが。 軽さに寄与しているのも間違いない事実です。フロントシフトレバーとディレーラーが足して約200g、インナーのチェーンリングが約30gにケーブルも足されるわけです。少なくともフロントシングルなら重い変速動作ともおさらばです。
リアディレイラー − SHIMANO 105 RD-5800
SHIMANOの105グレードのリアディレイラー、RD-5800-SS Blackです。
個人的にリアディレイラーは消耗しにくいパーツのひとつです。
ワイヤーシフトの11s用リアディレイラーならDURA-ACEからULTEGRA、105やMETREAまで公式に互換性があるため、さっさと上位グレードに交換してしまうのも手かと感じています。
その代わり、乗り手に大した非もない状況でディレーラーハンガーは突発的に逝くうえ、おいそれと代替品が手に入らないので、必ずストックを作るようにしましょう。 ロードバイクはこれで二度ほど苦しんでいます。
その代わり、乗り手に大した非もない状況でディレーラーハンガーは突発的に逝くうえ、おいそれと代替品が手に入らないので、必ずストックを作るようにしましょう。 ロードバイクはこれで二度ほど苦しんでいます。
| 項 目 | 内 容 |
| グレード | 5800系105 |
| タイプ | ロード用11スピード・HG-X11 |
| ロー側ギア対応 | 最大28T・最小23T |
| トップ側ギア対応 | 最大14T・最小11T |
| プーリーギア数 | 11T |
| 最大フロント差 | 16T |
| トータルキャパ | 33T |
| 機能 | ケーブルアジャスター、直付対応 |
| 公称重量 | 234g |
⇒ SHIMANO ROADリアディレイラー整備マニュアル(1.2MB)
⇒ SHIMANO RD-5800部品展開図(775KB)
チェーン − 公式名称なし
DAHON公式スペックにはチェーンが何か書かれていませんが、実物には「SHIMANO CN-HG601」と刻印があるので、SHIMANO CN-HG601-11がセットされているのが分かります。
私のMu SLXは数えてみると長さは110リンクでした。ただしチェーン落ちが頻発する対処として購入店で2リンク詰めてもらったので、元は112リンクだったことになります。
私のMu SLXは数えてみると長さは110リンクでした。ただしチェーン落ちが頻発する対処として購入店で2リンク詰めてもらったので、元は112リンクだったことになります。
| 項 目 | 内 容 |
| グレード | 記載なし(105) |
| タイプ | 11スピード・HG-X11 |
| ローラーリンク | フッ素加工あり |
| ピンリンク | フッ素加工なし |
| リンクピン | フッ素加工なし |
| ピン形状 | 非中空ピン |
| 公称重量 | 114リンク・257g |
⇒ SHIMANO 11スピードチェーン整備マニュアル(1.2MB)
カセットスプロケット − SHIMANO 105 CS-5800 11-28T
SHIMANOの105グレードの11sカセットスプロケット、CS-5800を搭載しています。ギアの構成は11-28T(11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T)。公称284g。 購入前の試乗レポートでも挙げましたが、特にカスタムしない状態のMu SLXのペダル1回転で進む距離は下表の通り。ペダルを漕ぐ重さの目安になります。これを手持ちの自転車と比べれば、概ねの傾向がイメージできます。 まぁ強引に言って、700Cロードバイクでフロントインナー39Tの走行感に近いと言えます。| 20in.(406)×1.25 | 28T | 25T | 23T | 21T | 19T | 17T | 15T | 14T | 13T | 12T | 11T |
| フロントギア数:55T | 2.85m | 3.19m | 3.47m | 3.80m | 4.20m | 4.69m | 5.32m | 5.70m | 6.13m | 6.65m | 7.25m |
※タイヤ周長:20x1.25(ETRTO32-406)=1,450mm。 参考:700x23C=2,096mm
…とはいえ、自分が乗っていたのは4500系TIAGRAコンポのロードバイク。9速、しかもローギアは整備不良で死んでいましたし、フロントはディレーラーを外してインナーしか使わない運用だったので、もう隔世の感があります。 リアの段数が増えると変速する機会も増える、それも9→10速より10→11速のほうが感じやすいとか前に聞いた気がしますが、9→11速ですからね。笑っちゃうくらい変速の機会は増えましたよ。 ギアの守備範囲が狭いというか、ちょっとペダルが重いかな?軽いかな?と感じてシフトチェンジするまでのタイミングが早いし、かなり漕ぐ力を一定に保てるようになりました。
⇒ SHIMANO カセットスプロケット 11スピード整備マニュアル(172KB)
⇒ SHIMANO CS-5800部品展開図(442KB)
ブレーキアーチ − Promax DHV-85
これもブラックボックスで、「DHV-85」で検索しても、本家PromaxのHPサイトで探しても情報が出てきません。見た目から分かることは、アーチ長が85mmで、ブレーキシューはカートリッジ式であること…くらいです。 まぁMTBではディスクブレーキに置き換わって久しいので、Vブレーキには大手の開発力が注がれません。上位パーツが出回らないのです。というか、DAHONのロゴが入っていますし、見た目はDahon Proの鍛造アルミ製Vブレーキ[Dahon Pro forged ultra light aluminum V brakes]と同じ物じゃないかと思うんですよね…。
ペダル − MKS Promenade EZY quick release
日本の高級ペダルメーカー、三ヶ島製作所の着脱可能なPromenade EZYペダルを搭載。
ロードバイクでシルバーの同じヤツを使っていましたよ…。いいですね、万が一破損しても予備があることに。まぁ欲を言えばPromenade Ezy(351g)ではなくて、さらに軽いCompact Ezy(302g)を採用して欲しかったところ。 "さらに"を重ねて、折りたたみ時にペダルを外す意味が少ない左ペダルをEzyシステムを採用していないOne Side Ezyモデルにしてくれれば、左右で267.5gと83.5gも軽くなったのに。 まぁOne Side EzyはCompact EzyではなくUX-D Ezyの話なので完全に妄想の産物です(^^)v。
ロードバイクでシルバーの同じヤツを使っていましたよ…。いいですね、万が一破損しても予備があることに。まぁ欲を言えばPromenade Ezy(351g)ではなくて、さらに軽いCompact Ezy(302g)を採用して欲しかったところ。 "さらに"を重ねて、折りたたみ時にペダルを外す意味が少ない左ペダルをEzyシステムを採用していないOne Side Ezyモデルにしてくれれば、左右で267.5gと83.5gも軽くなったのに。 まぁOne Side EzyはCompact EzyではなくUX-D Ezyの話なので完全に妄想の産物です(^^)v。
| 項 目 | 内 容 |
| カラー | ブラック |
| ボディ材質 | アルミダイキャストADC6 |
| 側板 | アルミ/塗装 |
| 軸サイズ | 9/16インチ(14.3mm) |
| サイズ | 踏み面横85 x 前後64mm |
| 踏み面 | 両面 |
| ベアリング | ボールベアリング |
| トゥクリップ | 取付可能 |
| リフレクター | 取付可能 |
| 重さ | 351g |
Ezy Superiorを採用しなかったのは英断としたいですね。アダプターにハメるときにパチンと自動でキャップが戻らない不具合レビューがあるのと、 Ezy SuperiorのほうがノーマルEzyより14g重いし、経験上はEzyストッパーを使わなくてもペダルは外れないためです。そもそもストッパーが外しにくすぎるんですよ…。
⇒ PROMENADE Ezy|自転車ペダルの三ヶ島製作所
その他
《 Base for Landing Gear 》
Landing Gearとは航空機が離着陸のときに出す車輪付きの脚のことです。それにあやかった「Landing Gear」というキャスターが取り付けられる台座(ネジ穴)を搭載していますよ、ということです。
本来はフレーム構造に付随することだと思いますが…。キックスタンド用の台座もあるのにBase for Kick Standとは書かれていないのも釈然としません。
ただ、5LINKS 169を使っていても思いますが、少なくとも日本国内の輪行において、折り畳んだまま転がせる機能はメリットが少ないです。
ただ、5LINKS 169を使っていても思いますが、少なくとも日本国内の輪行において、折り畳んだまま転がせる機能はメリットが少ないです。
まず、電車改札内ではフルカバーの輪行バッグがほぼ必須なことから、車体に転がせる構造があっても活用できないことが挙げられます。 また、改札を出ての乗換も長くて300m程度であり、フルカバー輪行袋から出してから転がし、再び収納してから改札を通るのは非常に手間です。 持ち上げて歩いたほうが早いし、それ以上の距離になったら普通に走行したくなるはず。 集合住宅なら、剥き出しの折りたたみ姿のままエレベーターに乗ったりと利点があるのでしょうかね。点字ブロックで躓きそうなくらいLanding Gearの車輪が小さいのも気になります。スーツケースじゃないんだからバランス激悪でしょうに…。
《 チェーンリテーナー 》
公式スペックには書かれていませんが、付属していました。リテイナー(Retainer)は保持という意味です。
チェーンキャッチャーと呼んだほうが分かりやすいでしょうかね。チェーンの内側に物を添えることで、フレーム側へのチェーン落ちを防止するパーツです。
このパーツ、Ternのほうがよくできています。Ternのは筒の中をチェーンが通る構造なので、フレーム側だけでなくクランク側に落ちるのも防いでくれます。
《 反射板・呼び鈴 》
これも公式スペックには書かれていません。…というか、おそらく日本で発売(走行する?)する自転車には反射板や呼び鈴を付けなければならない決まり事のようで、どんな自転車を買っても付属します。 付けてくれたのは購入店の橋輪さんでしょう。
正直言って格好悪いですし、こんなものにも確実に重さがあるので、速攻で外しました。 当然法的にアレなので自己責任ですし、クルマを運転する側に立てば反射板の有用性はよく理解できるので反射テープを貼ろうと思います。セーフティライトの日中点灯も習慣になればどうってことないですし。 ベルは、キャットアイのOH-2400をロードバイクから移植です。滅多鳴らすこともないのですが…これもポーズですよね…。





◆参照・引用
・千葉県柏市の自転車・車椅子ショップ 橋輪(はしりん)http://hasirin.com/index.html
・DAHON OFFICIAL SITE - ダホン 公式サイト
https://www.dahon.jp/index.html
・DAHON International - ダホンインターナショナル公式サイト
https://dahon-intl.jp/
・Folding Bikes by DAHON
https://dahon.com/
・SHIMANO Bike
https://bike.shimano.com/ja-JP/home.html
・SHIMANO Bike マニュアル&技術情報
https://si.shimano.com/#/
・gan well:岩井商会 Kalloy
http://www.iwaishokai.co.jp/list.php?mnfct_id=kalloy
・KCNC公式サイト
https://www.riteway-jp.com/pa/kcnc/
・DDK Group
http://www.activeddk.com/
・パナレーサー株式会社
https://panaracer.co.jp/
・Full Speed Ahead(FSA)
https://www.fullspeedahead.com/ja
・Promax Components
http://www.promaxcomponents.com/
・自転車ペダルの三ヶ島製作所
https://www.mkspedal.com/?q=ja
・American Classic
https://amclassic.com/
・Sapim
https://www.sapim.be/
購入経緯
試乗レポートへ
Mu SLX
トップへ
日常のメンテ
プチカスタムへ
Copyright(C) 2005-2018 Pickup=Lightup by Mars. All Rights Reserved.